みなさん、こんにちは。今回は春江一也著『プラハの春』のレビューを書きます。あれだけ推薦しておきながら、なかなか着手できませんでした。どうぞ、今回のレビューを参考にして、手に取ってみましょう。
① 『プラハの春』の基本はラブロマンス
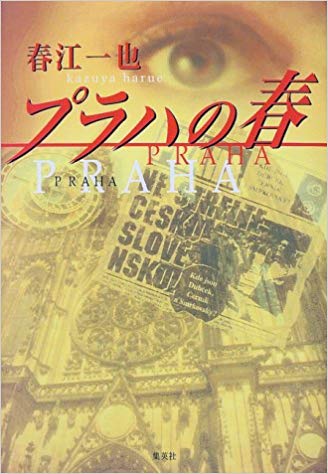
まずはあらすじから。『プラハの春』はジャンルで分けるならラブロマンスですが、同時に歴史小説でもあります。舞台は1967年、社会主義時代のチェコスロバキアです。
ここで、在チェコスロバキア日本大使館員の堀江と東ドイツの反体制活動家のカテリーナがふとしたきっかけで出会います。この出会いから1968年の夏まで壮大なドラマが展開されるわけです。
壮大なドラマの背景にあるのが「プラハの春」です。「プラハの春」とは1968年、ドプチェク第一書記による政治・社会改革を指します。よく、「プラハの春」を脱ソ連・資本主義化を目指した改革と勘違いされる方がいますが、それは間違いです。
ドプチェクはソ連を中心とする東側陣営にとどまりながら、チェコスロバキア流の社会主義を建設しようとしました。具体的には検閲の廃止、言論の自由、計画経済の見直しなどが挙げられます。
一方、あくまでも共産党がイニシアティブを取ることが前提。また、指導部の口からはハンガリーのような脱ソ連を意識するような発言は出ませんでした。
しかし、ソ連をはじめとする社会主義国はチェコスロバキアの改革を敵視します。周辺国は自分たちの体制に悪影響を及ぼしかねない、と考えたわけですね。1968年8月、ソ連は主権制限論(全体の利益は各国の国益より上回る)を振りかざし、ワルシャワ条約加盟国と共にチェコスロバキアに介入。超大国の圧力により「プラハの春」は終わりを迎えました。
少し話が長くなりましたが、ラブロマンスと同時に「プラハの春」をめぐる政治的な駆け引きが展開されます。どのように、2人のロマンスが政治的な動きに翻弄されるか。これが『プラハの春』の最大の見どころだと思います。
② ものすごくリアルな話の展開

『プラハの春』が支持を集めている理由のひとつに描写方法が挙げられます。読み進めると「これは筆者の実体験なのでは・・・」と思ってしまうのです。
それだけ、2人のやり取りや息遣い、政治的な緊張がダイレクトに伝わってきます。物語の後半には完全に堀江もしくはカテリーナに感情移入してしまうでしょう。それもそのはず。作者である春江一也さんは外交官で、1967年当時は在チェコスロバキア日本大使館に勤務していました。
ひょっとすると、カテリーナとの話も実話・・・と勘ぐりたくなりますが、そこはわかりません。あくまでもフィクション、ということにしておきましょう。
③ 『プラハの春』には続き話がある?

実は『プラハの春』には続き話があります。続編となるのが『ベルリンの秋』です。当たり前のことですが『プラハの春』を読んでから、『ベルリンの秋』を読んでくださいね。
せっかくですから『ベルリンの秋』にも少しだけ触れておきましょう。『ベルリンの秋』は堀江とカテリーナの娘、シルビアとのお話になります。ただし、『プラハの春』は好きだけど『ベルリンの秋』はちょっと・・・という方は多いようです。
個人的な感想を書くなら、『プラハの春』『ベルリンの秋』も含めて、これこそが「人間」だと思うのですね。同時に権力の怖さを感じられます。さて、ここ10年『プラハの春』を読んだ同年代(20代~30代)に会ったことがありません。『プラハの春』を読んだら感想を教えてください。

